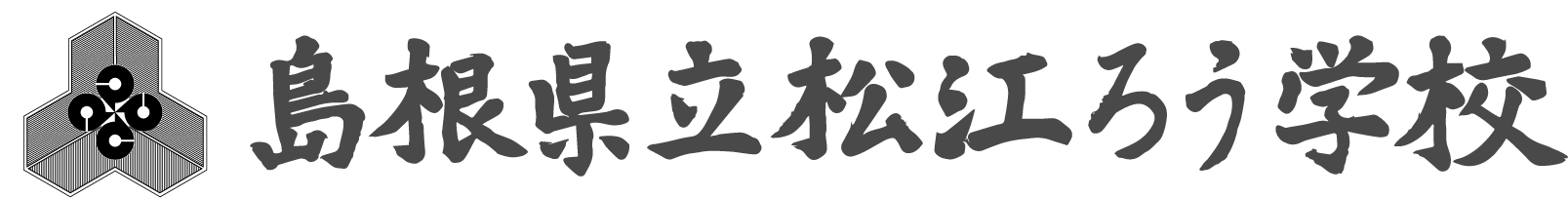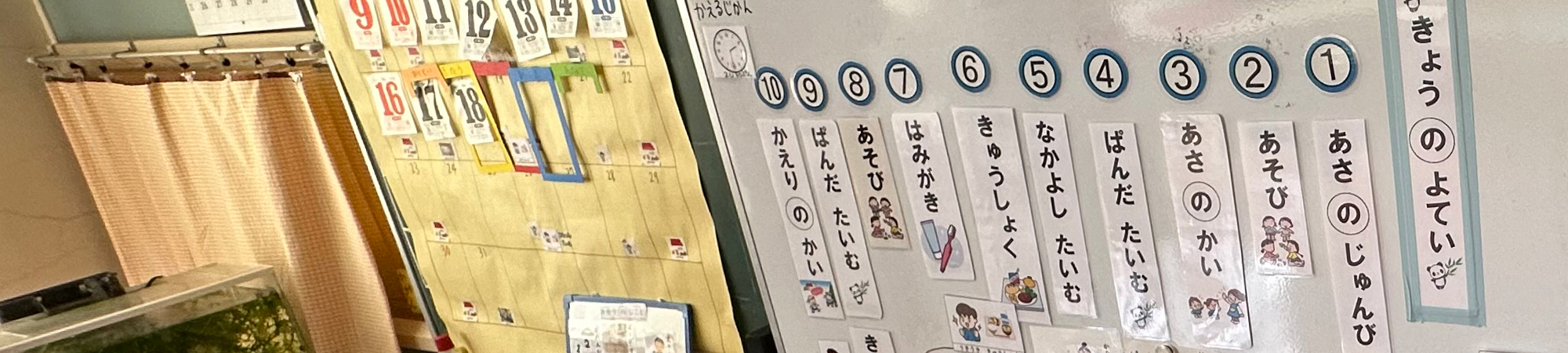-
寄宿舎 校外活動2023年10月30日
10月18日(水)に校外活動で、ジョリーパスタに出かけました。
事前の舎生会では、舎生だけで話し合いをして行き先を決めました。外出時のルールやマナー、服装についても意見を出し合い準備をしました。
当日は、タッチパネルを自分で操作し、注文をしました。今回は、大学生交流で交流をしている大学生の参加もあり、お互いに質問をし合い、そこから会話が広がり、にぎやかな雰囲気で食事をすることができました。
食事後に、自分が注文したものをスマホやメモに記入して、店員さんに伝わるよう、一人一人が工夫をして支払いを済ませる姿を、とても頼もしく感じました。
2時間の活動でしたが、舎生は思い思いに楽しみ、リラックスをした様子で過ごすことができた、寄宿舎ならではの行事だったと思います。
今回の経験が、今後の大学生交流や将来的な余暇活動につながっていくことを願っています。



-
稲刈りをしました!(小学部)2023年10月27日
10月24日、カンドーファームの田尻さんにお世話になり、稲刈りをしました。例年、古江小学校との交流学習で行っていますが、今年は予定が合わず、本校のみ後でさせてもらいました。最初に田尻さんから、鎌の使い方や稲の刈り方を教わり、その後自分たちでやってみました。田尻さんから「上手ですね。」と褒めてもらい、嬉しそうな表情を見せていました。稲刈りを始めるとあっという間に時間が過ぎ、帰校する時間になっても、「まだやりたい!!」という声が聞かれるくらい、楽しんで取り組んでいました。今日収穫したお米は、2学期末にカレーライスを作り、古江小の友達や田尻さんと一緒に味わう予定です。






-
手作りの味噌汁、おにぎりパーティ!(小学部) ~地域の方と共に~2023年10月26日
昨年度の2月、古志町にお住いの藤井さんに来ていただき、一緒に味噌を仕込みました。そして月日は流れて・・・10月18日、味噌樽を初めて開けてみました。藤井さんにも出来上がりを見てもらい、「とてもおいしくできています。」と言っていただきました。この味噌を使い、藤井さんと一緒に味噌汁作りをしました。
また、児童がバケツで育てた稲を脱穀、もみすりをした玄米を白米に混ぜておにぎりにし、味噌汁と一緒に味わいました。自分たちで作った味噌そして、お米で作った料理の味は格別だったようです。
今回、味噌作りを教えていただいた藤井さんとは、校外歩行で出会うと声をかけていただいたり、児童が招待状を出し、かきばら祭に太鼓の発表を見に来ていただいたりするなど、味噌作り以外でも交流を深めています。
今後も地域の方々のお力を借り、児童たちが様々な人との交流を楽しみながら、経験を積み、力をつけていけるような活動ができるとよいと考えています。






-
地域探検 四ツ葉園パン工場(小学部2―1)2023年10月24日
10月19日(木)に、地域探検で四ツ葉園のパン工場に見学に行きました。パン工場に着くと早速、「パンのいい匂いだね。」と嬉しそう。パン工場では、パン生地を機械に入れたり、形を作ったり、焼きあがったパンを運んだりする様子を見ることができました。「たくさんパンがあるね。」「あれは何パンかな。」「見て。」と、二人とも興味深々で見学しました。


そして、「美味しいパンは、どうやったらできますか。」「パンを作るのは、難しいですか。」と質問をして、パン作りについて、くわしく知ることができました。最後は、それぞれが好きなパンを買って帰り、帰るとすぐにパンを食べました。とっても美味しかったと伝えてくれました。

-
R5 寄宿舎 10月 本の時間2023年10月24日
10月16日(月)から20日(金)まで、学校の読書週間に合わせて寄宿舎では「本の時間」という取組を行っています。
今回は「食欲の秋」をテーマとし、旬の食材を扱った本や、世界の食文化に関する本、料理のレシピ本などを用意しました。
舎生からは、グルメ漫画『美味しんぼ』を手に取り、「読むとお腹が空いてしまう!」といった声や、世界の料理に関する本『しらべよう、世界の料理』を読んで、「おじいさんが、この国に行ったことがある。」と教えてくれるなど、様々なお話を聞くことが出来ました。
今後も本を通して、舎生の世界が少しでも広がるきっかけを作っていきたいと思います。

|